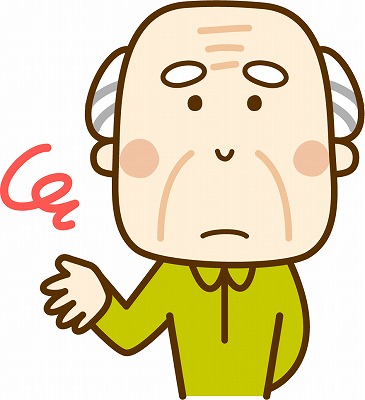
北海道横断自動車道の別保-尾幌間が2025年に着手することが決まったみたいだが、開通したら、私たちの暮らしや地域はどう変わるんだろう?
国土交通省は、北海道横断自動車道の釧路町・別保―厚岸町・尾幌間の高規格道路整備を2025年度に設計や測量など着手する方針を固めました。
昨年12月に、道東自動車道の阿寒ICー釧路西ICが開通し、札幌と釧路が高速道路でつながったことが大きなニュースとなりましたが、さらに東方への延伸がされることになります。
長年の課題だった移動時間の短縮、地域経済への効果を期待するとともに、いつ開通するのか?私たちの生活はどうなるのか?地域医療への影響は?などなど、少し不安を感じている方もいるかもしれません。こ
この記事では、北海道横断自動車道の別保-尾幌間の開通がもたらす未来について解説していきます。地域の発展にどうつながるのか、一緒に考えてみませんか?
2025年着手決定!北海道横断自動車道の別保-尾幌間

北海道横断自動車道は、道央の黒松内町を起点とし、道東の網走市・根室市を結ぶ高速道路です。このうち、厚岸町尾幌-同町糸魚沢間の「尾幌糸魚沢道路(延長24.7 km)」が、2019年度にすでに事業化されています。
道東自動車道と接続する別保-尾幌間は約21kmの区間であり、2025年に設計や測量などに着手する見通しとなっています。この区間が開通して道東自動車道と接続することで、広域的な交通ネットワークを形成されることになります。
●事業個所:北海道横断自動車道 釧路別保IC-厚岸町尾幌
●事業主体:国土交通省 北海道開発局
●延長:21.2km
●着手予定:2025年度
※2025年度は設計や測量などが行われる見通し
●事業費:約1250億円
●着工予定時期:未定
●開通予定時期:未定
●開通による時間短縮効果:根室市から釧路空港まで7分短縮
開通はいつ?変わる釧路・根室地域の未来

高速道路の事業化から開通までのスケジュールは、様々な要因によって大きく変動するため、一概に「〇年」と断言することは難しいようです。
事業化から開通までの一般的な目安期間は?
工事期間は、様々な要因で変動するため具体的な年数を出すのは難しいですが、一般的には、事業化決定から開通まで10年以上かかることが多いです。大規模なプロジェクトや、環境問題、用地取得などで難航する場合は、さらに長期間を要することもあります。
一般的な流れと各段階で考慮される要素を以下にまとめました。
1.計画段階(構想・調査)(済)
●構想
・高速道路ネットワークの必要性や、地域間の連携強化などの目的を検討
・交通量予測や環境影響などを考慮し、おおまかなルートや構造を検討
●計画調査
・交通量調査、地質・環境調査などを行い、具体的なルートやインターチェンジの位置などを検討
・地域住民への説明会や意見交換会などを開催
・費用対効果分析を行い、事業の妥当性を評価
●この段階で考慮される主な要素
・政策的な必要性:国土交通省の政策や、地域の開発計画との整合性
・交通量予測:将来的な交通需要の見込み
・環境への影響:生態系、景観、騒音などへの影響
・地質・地形条件:弱地盤の有無、急峻な地形の有無
・地域住民の合意:用地取得や工事への協力
・事業費:建設費、用地取得費、維持管理費
2.事業化決定←今回はココ!
●事業化決定
・計画調査の結果を踏まえ、国(国土交通省)が事業の採択を決定
・事業主体(NEXCO各社、地方道路公社など)が決定 ⇒ 今回は国土交通省
●この段階で考慮される主な要素
・費用対効果:費用に見合うだけの効果が見込めるか
・財源:事業費をどのように確保するか
・事業主体の能力:事業を円滑に進める能力があるか
3. 設計・用地取得
●詳細設計
・構造物の詳細な設計、地盤改良計画、環境対策などを決定
●用地取得
・高速道路建設に必要な用地を取得するための用地交渉、測量、鑑定評価などを実施
●この段階で考慮される主な要素
・詳細な地質調査:より詳細な地質調査を行い、最適な構造形式を決定
・環境アセスメント:環境への影響を最小限に抑えるための対策を検討
・用地交渉の難易度:地権者の数、権利関係の複雑さ、協力意向など
4. 建設工事
●建設工事
・橋梁、トンネル、道路本体などの建設工事
・安全管理、品質管理、工程管理を徹底
・工事期間中、周辺住民への影響を最小限に抑えるための対策を実施
●この段階で考慮される主な要素
・技術的な難易度:高度な技術や特殊な工法が必要となる場合
・気象条件:天候不順や自然災害の影響
・労働力不足:建設作業員の確保
・資材価格の変動:鋼材やコンクリートなどの価格変動
・埋蔵文化財の発見:工事中に埋蔵文化財が発見された場合
5. 開通準備・開通
●開通準備・開通
・道路施設の点検、標識・標示の設置、料金所の準備
・開通式典などを開催し、一般車両の通行を開始
●この段階で考慮される主な要素
・事業規模:全長が長いほど、工事期間も長期間に
・地形・地質条件:山岳部や軟弱地盤では工事が難航
・環境問題:環境保護団体や地域住民からの反対運動が起こると、計画の見直しや対策が必要
・用地取得の難易度:地権者との交渉が難航すると、用地取得に時間を要する
・予算の制約:予算が削減されると、工事の規模縮小や期間延長を余儀なくされる場合あり
・技術的な問題:難易度の高い工事では、技術的な問題が発生する可能性あり
・自然災害:自然災害が発生により工事の中断、復旧作業が必要になる場合あり
釧路・厚岸の地域住民の生活はどう変わる?

釧路や厚岸の地域住民にとって、この高速道路の開通によって「日常」「物流」「観光」の3つの点で大きな変化があると思われます。
日常の変化(通勤・買い物)
北海道横断自動車道の別保-尾幌間の開通は、地域住民の日常生活にも変化をもたらします。
厚岸町などから釧路市内へ通勤の時間が短縮され、より快適な生活を送ることができます。また、根室方面からの釧路市内への買い物や医療機関へのアクセスも容易になり、生活の利便性が向上します。
物流への影響(効率化とコスト削減)
別保-尾幌間の開通は、トラックによる物流の効率化とコスト削減に貢献します。
移動時間の短縮により、輸送時間の短縮や燃料費の削減が期待されます。特に、厚岸港でせいさんされる牡蠣や根室港で水揚げされるサンマなどの水産物は鮮度が重要な商品であるので、釧路港への輸送において大きなメリットがあります。
観光業への影響(新たな観光ルートの誕生)
別保-尾幌間の開通は、道東地域の広域観光に大きく貢献します。
これまで、釧路市から時間がかかっていた厚岸町の道の駅コンキリエや浜中町・霧多布岬、根室市・納沙布岬など各地へのアクセスが容易になり、広域的な観光周遊が可能になります。また、新たな観光スポットの開発や、既存の観光資源の活用も進むでしょう。
釧路市周辺の地域医療はどう変わる?

道東地域は大きな病院が釧路市内に集約されていることから、周辺市町村からの救急搬送や通院に大きな影響を与えると思われます。
救急医療機関へのアクセス向上
別保-尾幌間の開通により、救急医療機関へのアクセス向上に大きく貢献します。
従来の国道44号よりも線形がよくなることから、これまで時間がかかっていた救急搬送が迅速になり、救命率の向上につながります。特に、重症患者や緊急性の高い患者の搬送において、大きな効果が期待されます。
地域医療体制の強化
別保-尾幌間の開通により、地域医療体制の強化にもつながります。
釧路市の病院と各市町村の医療機関の移動効率化により、医療従事者の行き来が容易となり、医療機関の連携が強化され、地域医療全体の質の向上が期待されます。
筆者のつぶやき

2025年度に、北海道横断自動車道の別保-尾幌間の設計や測量などに着手することが決まりました。
事業化から開通までは最低でも10年ほどかかるため、まだまだ先の話ですが、地域医療や観光面など生活に大きな影響があることは間違いなさそうです。

keimei
大阪府出身、北海道に移住して12年目。道内各地を転々とし、現在は道東に在住。2024年12月に北海道観光マスター検定、2025年3月に北海道フードマイスター検定合格。
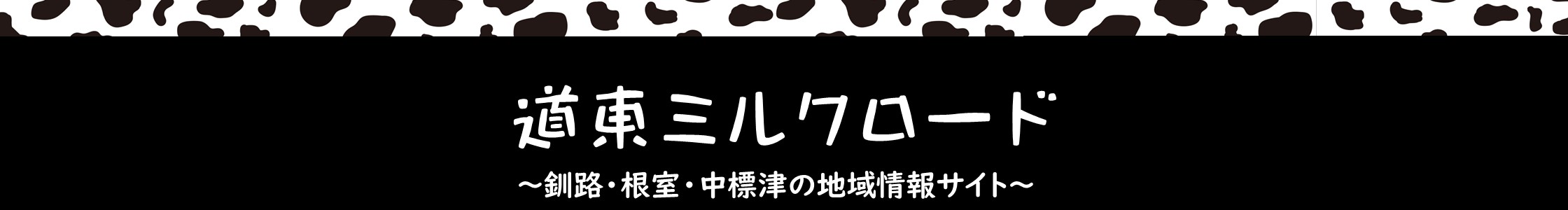



コメント